今日は、地元の図書館、県の図書館のあらゆる本を探しても、神社のいわれがさっぱりわからないので、地元のの公民館に行って聞いてみることにしました。ある磐座(いわくら…信仰対象となっている巨岩)の下に祠があり、それが何の神社なのか、そればかり気になっています。
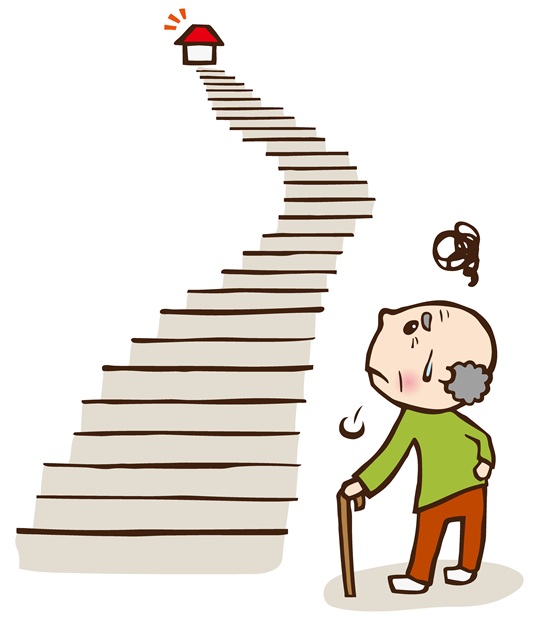
地元の人に聞いたりはあまりしない
私は、あまり地元の人たちの話を聞いたりしません。道を聞いたりはしますが、聞いても、詳しくわかっているのに出会うのが難しいのと、たいへん気を使うからです。
だから、ほとんど、図書館の古い地誌とか、江戸時代の本を読んだりします。
しかし、図書館の本(地誌、地元の歴史研究書、登山の本、観光の本等)見ても、何にもわからないので、この度公民館に行って聞くことにしました。30分ぐらいお話を聞きました。
自分のために時間をとってくださりありがたいです。
しかし、地元の人に聞いても、神社のいわれはわかりませんでした。地元でなんと呼ばれているかぐらいです。でも、そういうことはあります。よくわからなくても、掃除したり、お供えをする神社がよくあります。50年前だったら、そういうことを知っている、いわゆる古老という方々がおられたかもしれません。
慣れないことしたので、少し疲れました。
いまだ脚力や体力はある!長い神社やお寺の石段
遠出して話を聞いたついでに、近くの古い神社やお寺を参拝しました。自分の頭の中にいくつか古代史のテーマがあって、いずれ記事にしようと思っている神社やお寺です。
しかし、古い神社やお寺というものは、山の中の高い場所にあるのがほとんどです。
だから、石段がどれだけ登ったらつくだろうと思うと、気が遠くなります。
自分の年を数えよう。多少、気が遠くなるのが弱まります。1、2‥‥65・・・年齢と思うと、自分も65まではなんやかんや生きて来れたなあと、感慨深い気持ちになります。
物心ついた時、小児喘息で病弱な子でした。今朝の朝ドラの、やなせたかしさんの子役みたいな感じだったんだろうなあと思います。たまにしか、小学校に行かないので、転校生みたいな感じでした。
結局3つの神社やお寺の石段を登りました。一番長いのは、150段ぐらいありました。
あまり息切れもしないし、足も痛くないです。思ったより、まだ体力や脚力はあるんだなと再確認しました。
最後までお読みくださりありがとうございました。
⇩ 応援のクリックをぜひお願いします。
にほんブログ村

